島根県松江市、1300年以上の歴史を誇る「神の湯」玉造温泉の奥深く、玉湯川のほとりに静かに佇む古社があります。その名は「玉作湯神社(たまつくりゆじんじゃ)」。ここは、ただ願い事が叶うと人気のパワースポットというだけではありません。日本の建国神話、古代のハイテク産業、そして人々の祈りが幾重にも織りなす、壮大な歴史の物語が秘められた聖地なのです。
本記事では、この玉作湯神社の神話と歴史を深く掘り下げ、なぜこの地がこれほどまでに重要視されてきたのか、そして現代において多くの人々を惹きつける「願い石」の力の源泉はどこにあるのかを解説します。
神話の源流 祀られる神々と皇室の至宝「八坂瓊之勾玉」
玉作湯神社の本質を理解するには、まずそこに祀られる神々を知る必要があります。この神社の祭神は、単なる地域の守護神に留まらない、日本の神話体系において極めて重要な役割を担う神々です。
玉作りの祖神・櫛明玉神(くしあかるたまのかみ)と天岩戸神話
主祭神の一柱は、櫛明玉神。またの名を玉祖命(たまのおやのみこと)とも呼ばれる、古代の玉造り職人集団「玉造部(たまつくりべ)」の祖神です 。この神の名が日本の歴史の表舞台に大きく登場するのが、有名な天岩戸(あまのいわと)神話です。
『古事記』や『日本書紀』によれば、太陽神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)が弟・須佐之男命(すさのおのみこと)の乱暴に怒り、天岩戸に隠れてしまったことで、世界は闇に閉ざされます 。困り果てた八百万の神々は、天照大御神を外に誘い出すための策を練ります。この時、神々の叡智を結集した神・思金神(おもいかねのかみ)の指示のもと、様々な神宝が作られました。その中で、櫛明玉神が製作を命じられたのが、「八尺瓊之勾玉(やさかにのまがたま)」でした 。
この勾玉は、後に天照大御神が孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を地上に降臨させる「天孫降臨」の際に、八咫鏡(やたのかがみ)、草薙剣(くさなぎのつるぎ)と共に授けられ、三種の神器の一つとして、今も皇位継承の証として受け継がれています 。
玉作湯神社が櫛明玉神を祀るということは、この地が単なる勾玉の生産地ではなく、皇室の権威の根源ともいえる神宝を生み出した神の霊統を受け継ぐ、極めて神聖な場所であることを意味しているのです。
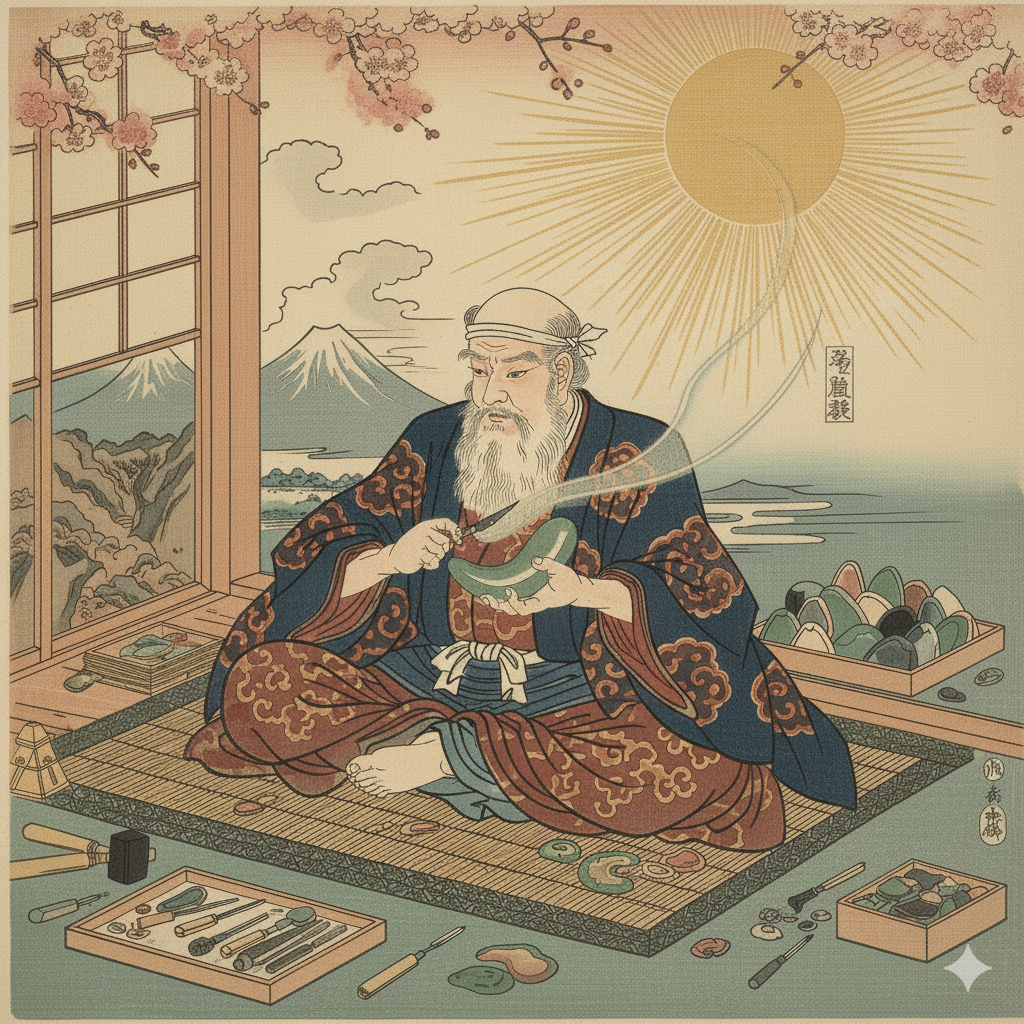
国造りの神々と温泉の発見 大名持神と少彦名命
次に重要なのが、大名持神(おおなもちのかみ)と少彦名命(すくなひこなのみこと)です 。大名持神は、出雲神話の英雄・大国主命(おおくにぬしのみこと)の別名で知られ、少彦名命と共に日本の国造りを行った偉大な神です 。
伝承によれば、この二柱の神が玉造の地を訪れた際に温泉を発見し、人々にその治癒の力を広めたとされています 。奈良時代に編纂された『出雲国風土記』には、玉造の温泉が「一度沐浴すればたちまち姿も麗しくなり、再び浴びればどんな病気もすべて治る」と記され、「神の湯」と呼ばれていたことが記録されています 。この記述は、温泉が古くから神々の恩寵と見なされていたことを示しており、大名持神と少彦名命の奉斎は、この地が持つ治癒の力の神聖性を保証するものなのです。

産業と国際交流の神 五十猛命(いそたけるのみこと)
境内には、韓国伊太氐神社(からくにいたてじんじゃ)という社も鎮座しており、ここには五十猛命が祀られています 。五十猛命は、父である須佐之男命と共に朝鮮半島から樹木の種を持ち帰り、日本全土を緑化したとされる神で、林業や産業繁栄の守護神として信仰されています 。
注目すべきは「韓国(からくに)」という社名です。これは古代における朝鮮半島との技術的・文化的交流を示唆しており、玉作りの技術にも大陸からの影響があった可能性を物語っています 。五十猛命の存在は、この地が単なる国内の生産拠点に留まらず、古代の国際的な技術交流の結節点であった可能性をも示しているのです。

これら四柱の神々は、「工芸(玉作り)」「健康・観光(温泉)」「産業(林業・殖産)」という、古代出雲の経済と文化を支えた三大要素を完璧に網羅しています。玉作湯神社は、まさにこの地域の営みそのものを神格化した、生きた信仰の殿堂なのです。
歴史の奔流 古代国家から松江藩主まで
玉作湯神社の歴史は、日本の国家形成と深く関わりながら、時代と共にその役割を変容させてきました。

『風土記』と『延喜式』に記された国家の公認
神社の名が歴史書に初めて登場するのは、天平5年(733年)頃に成立した『出雲国風土記』です。意宇郡の条に「玉作湯社(たまつくりのゆのやしろ)」と明確に記されており、この時点で既に「玉作り」と「温泉」という二つのアイデンティティが確立していたことがわかります 。
さらに、延長5年(927年)に成立した、朝廷が公認した神社のリストである『延喜式』神名帳には、「玉作湯神社」と「同社坐韓国伊太氐神社」の二社が記載されています 。これは、平安時代の朝廷から国家的に重要な神社(式内社)として認められていたことを示す、最高の栄誉です。
また、平安時代の歴史書『日本三代実録』には、貞観元年(859年)と貞観13年(871年)に、朝廷からこの神社の神階(神様のランク)が引き上げられた記録が残っており、中央政府がいかにこの地を重要視していたかが窺えます 。
中世・近世 温泉の守護神「湯船大明神」へ
中世から江戸時代にかけて、神社は「湯姫大明神」や「湯船大明神」といった名前で呼ばれるようになります 。これは、玉造りの産業が徐々に衰退する一方で、玉造温泉が湯治場としてますます重要視されるようになった社会情勢を反映していると考えられます。
特に江戸時代には、松江藩主・松平家から篤い崇敬を受け、歴代藩主が湯治に訪れる際には必ず参詣したと記録されています 。藩の最高権力者からの庇護は、神社の地位を不動のものとしました。
近代 古名への回帰と地域の象徴へ
明治維新後、社名は再び古代の記録に倣い「玉作湯神社」へと復されました 。近代社格制度では当初村社でしたが、その由緒と格式が認められ、昭和3年(1928年)には県社へと昇格しました 。これは、玉作湯神社が単なる一地域の神社ではなく、島根県を代表する重要な社であることを公的に示したものです。現在見られる荘厳な大社造の本殿は、この近代化を目前にした安政4年(1857年)に再建されたものです 。
玉作りの聖地 国の史跡「出雲玉作跡」との一体性
玉作湯神社の境内地は、実はそれ自体が国の史跡「出雲玉作跡(いずもたまつくりあと)」の一部として指定されています 。これは、神社が単に遺跡の近くにあるのではなく、歴史的生産現場と信仰空間が一体不可分であることを示しています。
古代日本のハイテク工房群
出雲玉作跡は、弥生時代末期から平安時代にかけて、碧玉やメノウを加工し、勾玉や管玉などを生産した日本最大級の工房跡です 。ここで作られた玉製品は、出雲国内だけでなく、大和王権をはじめ日本各地の有力者のもとへ供給され、祭祀や権威の象徴として用いられました。

神社の境内には、古代の住居形埴輪を模した「出雲玉作跡出土品収蔵庫」があり、周辺遺跡から出土した約700点もの貴重な資料が収蔵されています 。その中には、未完成の玉類や砥石など、玉作りの工程を知る上で極めて重要な遺物が含まれ、国の重要文化財に指定されています 。これらの遺物は、地域住民が発見のたびに神社へ奉納してきたものであり、神社が地域コミュニティの歴史遺産を守る中心的な役割を果たしてきたことを物語っています。
願いを叶える聖石 「願い石」と現代の祈り
玉作湯神社を現代において最も有名にしているのが、境内に祀られる「願い石(ねがいいし)」の存在です。この丸い自然石は、古来「真玉(まだま)」と呼ばれ、人々の信仰を集めてきました 。

聖石の伝承と現代の儀式
伝承によれば、石を加工する技術が未熟だった時代に、この完璧な球形の石が近くの山から現れたため、神が宿る御神体として祀られるようになったといいます 。社伝では、この石には祭神・櫛明玉神の御霊が宿るとされています 。
この「願い石」を中心とした祈りの儀式は、現代の参拝者のために体系化されたものです。
- 社務所で、小さな天然石が入った「叶い石(かないいし)」のセットを授かります 。
- 願い石の下から湧き出る御神水で、授かった「叶い石」を清めます 。
- 清めた「叶い石」を「願い石」に直接触れさせ、心の中で願い事を唱えます 。
- 複写式の願い札に願い事を書き、1枚を拝殿に納め、もう1枚を「叶い石」と共にお守り袋に入れて持ち帰ります 。
この一連の作法は、古代のアニミズム(自然物への畏敬)と、現代人が求める参加型でパーソナルなスピリチュアリティを見事に融合させたものです 。古代の職人たちが良質な玉の完成を祈ったであろうこの場所で、現代の私たちもまた、自分だけの願いを込めたお守りを作ることができるのです。この卓越した伝統の再解釈こそが、玉作湯神社が今なお多くの人々を惹きつけてやまない理由の一つでしょう。
周辺の史跡・神社仏閣を巡る
玉作湯神社を訪れたなら、ぜひ足を延ばしてほしい関連スポットが周辺に点在しています。これらを巡ることで、この地の歴史と文化をより立体的に理解することができます。
出雲玉作史跡公園と出雲玉作資料館
神社の東側の丘陵地帯には、出雲玉作史跡公園が広がっています 。公園内には、玉作り工房跡の保存施設や復元された竪穴住居などが点在し、古代の職人たちの息吹を感じることができます。
公園の中心施設である松江市出雲玉作資料館では、遺跡からの出土品が体系的に展示されており、玉作りの技術や歴史について深く学ぶことができます 。
清巌寺(せいがんじ)とおしろい地蔵
玉作湯神社のすぐ隣に位置するのが、臨済宗の寺院・清巌寺です 。このお寺で有名なのが、美肌にご利益があるとされる「おしろい地蔵さま」 。その昔、顔にあざがあった和尚がお地蔵さまにおしろいを塗って祈願したところ、あざが綺麗に治ったという伝説に由来します 。自分の体の気になる部分と同じ場所におしろいを塗って祈願するというユニークな参拝方法で、特に女性に人気のスポットです。

徳連場古墳(とくれんばこふん)
温泉街の東の林の中に、徳連場古墳という5世紀代の円墳があります 。玉作遺跡のすぐ近くにあることから、被葬者は玉作りと密接な関係にあった有力者だと考えられています。舟形の石棺が特徴で、古代の玉作り集団のリーダーの姿を想像させます。
布吾彌神社(ふごみじんじゃ)
玉作湯神社の境外社で、玉造温泉街のはずれの丘の上に鎮座する小さな神社です 。『出雲国風土記』や『延喜式』にも記載がある式内社の論社(候補地)の一つとされており、ひっそりとした佇まいの中に古代の面影を色濃く残しています。

玉作湯神社への訪問ガイド
アクセス
- 所在地: 〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造508
- 公共交通機関でのアクセス:
- JR山陰本線「玉造温泉駅」で下車。
- 駅から一畑バス玉造温泉行きに乗車し約7分、「玉造温泉」バス停または「姫神広場」バス停で下車、徒歩3〜5分 。
- 駅からタクシーを利用する場合は約5〜7分です 。
- 駅から徒歩の場合は約30分かかります 。
- 車でのアクセス:
- 山陰自動車道「松江玉造IC」から国道9号線を経由して約10分 。
- 駐車場: 神社前に約20台収容可能な無料駐車場があります 。
6.3 参拝時間と社務所受付
- 社務所受付時間:
- 平日: 9:00~12:00 / 13:00~17:00
- 土日・祝日: 8:30~17:00
- ※「叶い石」の授与や御朱印の拝受は、上記の受付時間内に限られます。時間は変更される可能性があるため、公式サイト等で最新情報をご確認ください 。
参考文献とさらに深く知るための書籍
玉作湯神社と出雲の歴史にさらに深く触れたい方のために、おすすめの書籍をご紹介します。
- 『出雲国風土記 全訳注』荻原千鶴 (講談社学術文庫)
- 『島根県の歴史散歩』島根県の歴史散歩編集委員会 (山川出版社)
- 島根県内の史跡や文化財をエリア別に詳しく解説したガイドブック。玉作湯神社や出雲玉作跡についても、歴史的背景と共に紹介されています。実際に現地を巡る際に非常に役立ちます 。
- 山川出版社オンラインショップで購入
- Amazonで購入


コメント